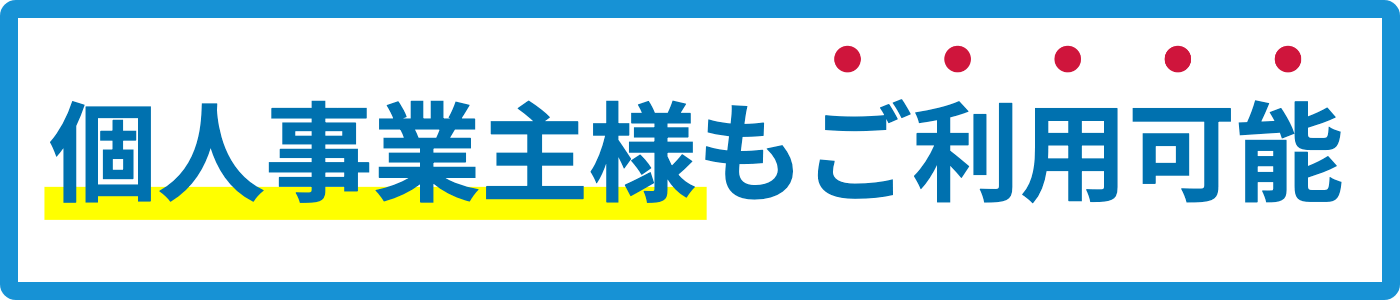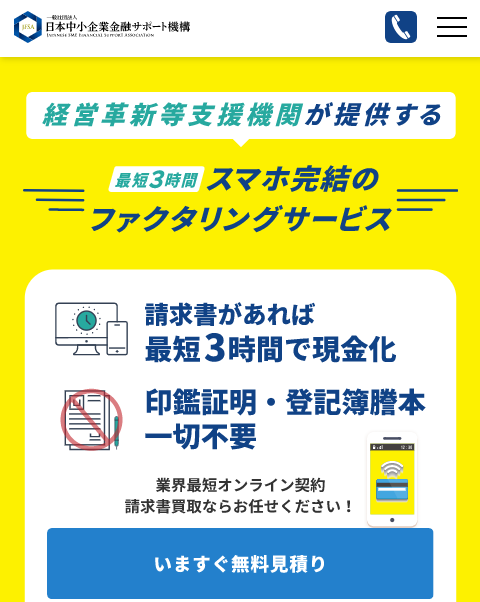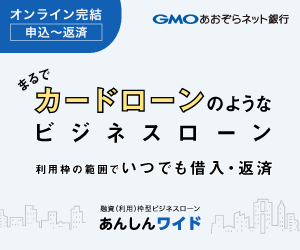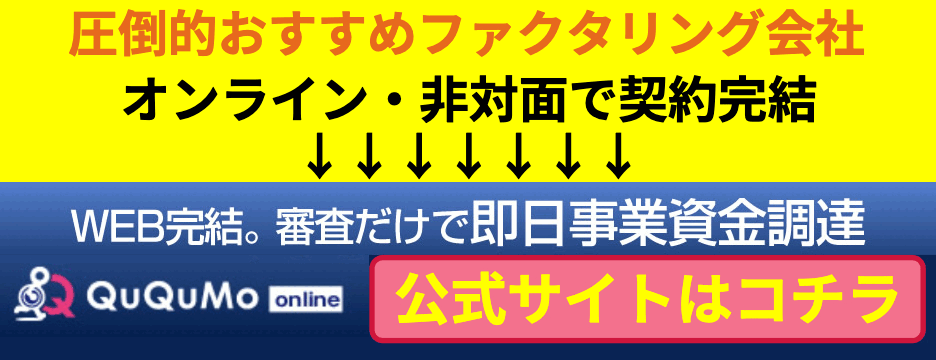- キャッシュフローの改善: ファクタリングは、即時性を持った資金調達方法です。企業は売掛金を現金に換えることで、資金繰りを速めることができます。
これにより、事業運営資金の調達、在庫購入、人件費支払い、新たなビジネスチャンスへの投資などに迅速に対応することが可能となります。
- 財務健全性の向上: ファクタリングはバランスシートを改善する効果があります。
売掛金を即座に現金化することで、負債を増やさずに自己資本比率を維持することが可能となります。これは、企業の財務健全性を評価する際に重要な要素であり、クレジットスコアの改善にも寄与します。
- リスク管理: ファクタリングを利用すると、売掛金の回収リスクをファクタリング会社に移転することができます。
これは、特に顧客が支払いを遅らせるまたは倒産する可能性がある場合に有効です。また、多くのファクタリング会社は信用調査も提供しており、これにより企業は取引先の信用リスクを評価し、リスク管理をより効果的に行うことができます。
ファクタリングのご利用を検討されている方にご注意いただきたいことは、ファクタリング会社の中には手数料が高かったり、広告とは異なり対応が遅かったりと、利用した方とトラブルになるケースも少なくありません。
そこで以下に、本当にオススメできる、安心してご利用いただける優良ファクタリング会社をご紹介させていただきますのでご参考にして下さい。
【PR】
 第1位 QuQuMo(ククモ)
第1位 QuQuMo(ククモ)売掛金前払いサービス QuQuMo(ククモ)とは?
「お持ちの請求書」を最短2時間でスピーディに現金化する売掛金買取サービスです。
QuQuMoなら、必要情報と請求書をオンライン申請していただくだけで、簡単にお申込いただけます。
来店や面談で、お申込みから契約までオンライン上のクラウドサインで安全に契約完結します。さらに、当社との直接の2社間ファクタリングなので、取引先への通知や登記は一切不要で、請求書の売掛先 に知られることなく資金調達ができます。
弁護士ドットコム監修、クラウドサインでの契約締結なので安心。
情報が外部に 漏れることは一切ありません!
売掛先の倒産リスクも含めてお買取をさせていただきますので、お客様に返済の義務はございません。QuQuMo(ククモ)ではノンリコース【償還請求権なし】での契約になりますのでご安心ください
| 総合評価 |
|---|
 第2位 メンターキャピタル
第2位 メンターキャピタル365日 24時間 全国対応
他社で断られた経験のある方も1度ご相談ください!
Mentor Capitalは、ファクタリングでお客様をサポートいたします。
手数料は最低2%~、
多数買取実績があり、
どこよりも高い金額にて売掛金を買取ります。
<< 選ばれる3つの理由 >>
1、買取実績 業界No.1
業界最低水準の手数料 買取率最大98%
2、簡単審査 柔軟な対応
赤字・債務超過・個人事業・税金滞納でもOK!・審査通過率92%
3、業種別適正プラン
30万円~1億円まで対応
2社間ファクタリングなら取引先に通知不要!!
2社間・3社間ファクタリングや「診療報酬」と「介護報酬」の売掛金買取など様々なご提案が可能です。
お客様の事業に特化したファクタリングサービスで最適な資金調達をサポートいたします。
| 総合評価 |
|---|
 第3位 資金調達プロ
第3位 資金調達プロ提携事業者数No.1
資金調達プロの提携事業者数は、国内最多の1,000社以上。
「資金調達」だけに特化した日本初にして日本最大級のポータルサイトです。
日本全国、どちらの地域でも対応しております。
資金繰り改善率93%以上
ファクタリングによるつなぎ資金での資金繰り改善はもちろん、財務コンサルティング後、その他の資金調達も可能。
銀行融資の再開も出来るようになり、多方面での資金調達・経営サポートが可能です。
全国対応
日本全国、どちらの地域でも対応しています。
遠方の経営者様も是非、無料診断をご活用下さい。
| 総合評価 |
|---|
 第4位 CoolPay(クールペイ)
第4位 CoolPay(クールペイ)お手元の法人宛の請求書を
最短60分で現金化できます
1.請求書・通帳をカメラで撮影して送るだけ
お手元の請求書・通帳3か月分をスマホカメラで撮影してお送りください。
2.ビジネスに必要な資金をすぐに調達できます
独自のオンライン申込専用の審査基準で スピーディに審査いたします。
3.必要な時に何度でも利用OK
資金繰りが厳しい時に何度でも利用できます。
| 総合評価 |
|---|
 第5位 ビートレーディング
第5位 ビートレーディング日本全国スピーディーに対応可能です。
お持ちの売掛金を売却することで、支払期日より前に資金化したり、売掛金の未回収リスク軽減を図るサービスです。
融資とは異なり信用情報に影響せず、審査も柔軟であるためスピーディーな資金調達が可能です。
必要書類はたった2点!
1.売掛債権に関する資料(請求書、注文書など)
2.通帳のコピー(表紙付2か月分)
審査結果は資料をご提出いただきましたら平均30分以内にお伝えします。
申込から契約までオンラインで完結するため、無駄なコストや手間はかかりません。
申込から最短2時間でお振り込みいたします。
| 総合評価 |
|---|
 第6位 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構
第6位 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構当機構へ請求書を売却し、即現金化することができます。
オンライン契約のファクタリングを利用を利用することにより、「スマホで簡単に即現金化できた」など、資金繰りにお悩みがあった企業様のサポートを実現いたしました。
資料提出や契約はすべてメールで完結するため、迅速な取引が可能です。
お申込みから最短3時間以内でお振込みが完了します!
<< 業界最低の手数料1.5%~ >>
オンライン契約で業務を効率化することにより、無駄なコストを削減し業界最低手数料1.5%~を実現しました。
<< 今後の取引に悪影響なし!売掛先の承認不要!! >>
利用社と当機構の2社間で契約をするため、売掛先へファクタリングを利用する承認が不要です。
今後の取引に悪影響が出る心配がありません。
| 総合評価 |
|---|
 第7位 株式会社エスコム
第7位 株式会社エスコム・最短即日で全国対応しており、出張買取、郵送、WEBでのご契約などお客様に合わせて柔軟に対応致します。
・償還請求権の無いノンリコースでお客様に保証を求めない契約なので、万が一売掛先が倒産した場合の支払いリスクを回避できるメリットがあります。
・銀行などの融資と違い、借入をするわけではないので、赤字決算・税金の未納・銀行をリスケ中でもご契約できます。
担保、保証人はありません。ですので売掛金さえあればご契約出来るというメリットがあります。
・スピーディーに丁寧なご対応させて頂きます。
借入ではない新しいかたちの事業資金調達方法「ファクタリング」。
契約をWEB完結(弁護士ドットコム社のクラウドサイン)にする事によって圧倒的なスピードで入金が可能です。
| 総合評価 |
|---|
 第8位 LINK
第8位 LINK事業主様が保有している入金待ちの請求書を、素早くお買取り資金化いたします!
必要資料をアップロードするだけで、誰でも簡単にお申込みいただけます!
LINKのファクタリングは、柔軟な審査と業界最速級のスピードが最大の特徴です。
お申込みと同時に必要資料をアップロード後、最短2時間で資金化が可能となった、オンライン完結型の新たなファクタリングサービスです。
弁護士ドットコム株式会社が運営する弁護士監修の「クラウドサイン」サービスを用いて電子契約を締結するから安心!!
万全なセキュリティー対策がなされたクラウドサイン契約システムを使用する事により、情報が外部に漏れることは一切ありませんので安心してお使いいただけます。
| 総合評価 |
|---|
 第9位 ネクストワン
第9位 ネクストワン来店不要で、30万円〜1億円以上のお客様のニーズに合わせた資金調達が可能です。
最短即日資金調達可能
スピード対応・スピード審査・スピード振込
業界最低水準の手数料
ファクタリング手数料1.5%〜
日本全国・様々な業者様に対応
ネクストワンのファクタリングは、日本全国の建築、建設、IT、医療、福祉など様々な業種のお客様にご利用いただいております。
遠方のお客様でもメールやFAXなどで資金繰りの専門家が対応いたします。
ネクストワンではネット上のみで契約が完結しますのでご来店は不要です。
| 総合評価 |
|---|
 第10位 トップ・マネジメント
第10位 トップ・マネジメント2、<>地方のお客様の成約時交通費キャッシュバック(日本全国対応しております)
3、製造業、建設業、システム開発業などに多い3か月以上の長期の支払いサイトにも対応
詳細な個人情報を入力する必要がなく、まだ電話相談も成果報酬対象となっておりますので非常に成果が発生しやすくなっております。
<<業界屈指のスピードファクタリング>>
お申込みから実行に至るまでのスピードはどこにも負けません。
最短即日、夕方にお申込み頂いたとしても、夜間のキャッシュデリバリーにて、その日の夜にはお客様の元に安心が届きます。
| 総合評価 |
|---|
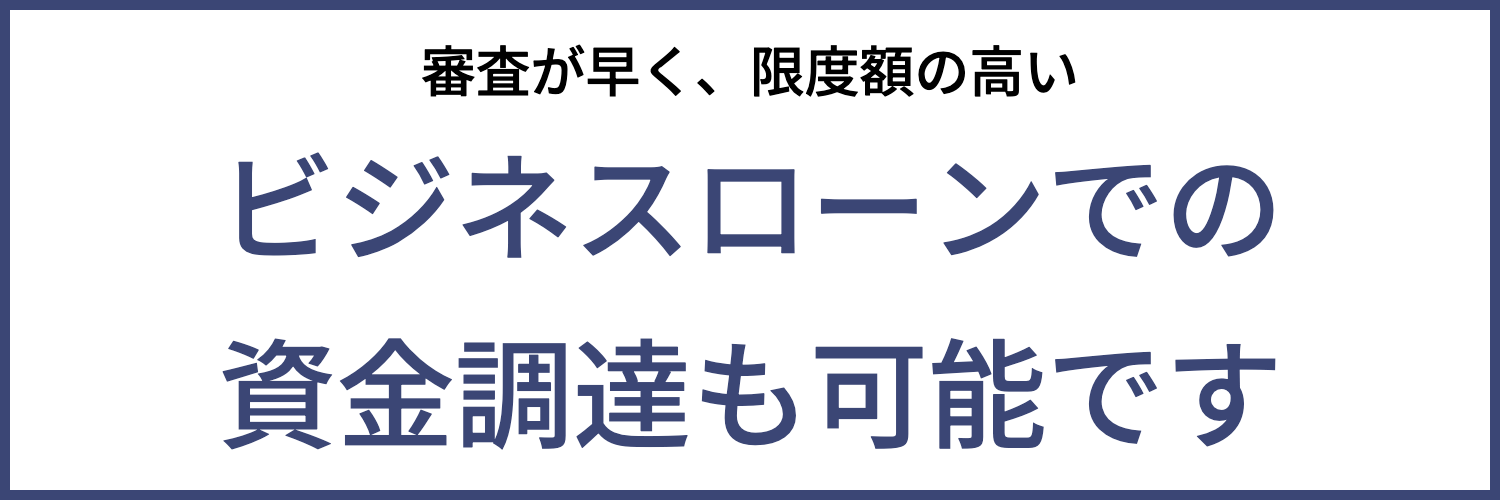
【PR】
 事業者向け【AGビジネスサポート】
事業者向け【AGビジネスサポート】原則無担保無保証・即日ご融資可能
<<ビジネスサポートの特長>>
年会費・保証料無料・・・年会費や保証料などは必要ありません。安心してお申込みいただけます。
保証人・担保原則不要・・・個人事業主様の場合は、その他保証人を立てていただく必要はありません。
資金用途自由・・・事業資金の範囲内で、自由にご利用いただけます。
申込から融資まで来店不要・・・お申込みからご融資までご来店は原則不要です。WEBと郵送で手続きが完了します。
| 総合評価 |
|---|
 GMOあおぞらネット銀行の融資枠型ビジネスローン【あんしんワイド】
GMOあおぞらネット銀行の融資枠型ビジネスローン【あんしんワイド】創業期や赤字でも借りられる!融資枠型ビジネスローン
<<【あんしんワイド】の特長>>
金利0.9%~、最大1,000万円の借入限度額・・・融資枠(借入限度額)は最大1,000万円。金利は0.9%~14.0%。審査のうえ決定します。事業資金、運転資金、つなぎ資金などにご利用いただけます。
決算書・事業計画・担保・保証人※不要で審査・・・銀行口座の直近3カ月分の入出金明細等をもとに審査します。そのため、決算書や事業計画書のほか、担保・保証人も不要です。創業初期や前年度が赤字の企業でもお借り入れいただけます。
審査申込~借入まで最短2営業日でネット完結・・・審査申込~お借入まで最短2営業日。 しかも、24時間365日*お申込可能。お手続きは来店不要。すべてオンラインで完結します。
| 総合評価 |
|---|
 法人事業者専用ローン【アクトウィル】
法人事業者専用ローン【アクトウィル】審査は最短60分
来店不要で全国即日OK
最短即日契約可能です!
只今、新規貸付キャンペーン実施中!!
アクト・ウィルならお申し込みから最短即日融資が可能です
<<アクトウィルが多くの事業主様に選ばれる4つの理由>>
理由1:無担保・無保証
法人契約になるので、代表者様の連帯保証があれば、その他の保証人・担保は原則不要です。
理由2:大口の融資が可能
借入一本化(他社からの借金をアクトウィルにまとめて、借金返済をスムーズにする債務整理法)に注力しています。このような、事業主様にとって健全な事業資金繰りをしていただくため、大口の融資が可能になります。
理由3:即日融資が可能
弊社の自慢はスピーディな対応です。他社よりも迅速に融資実行いたします!
理由4:低金利でご融資
事業主様と多岐にわたるお付き合いを考えています。そのため、事業計画にとって負担にならない【低金利】での融資額を、弊社担当者と事業主様の相談ベースで決定し融資を実行します。
| 総合評価 |
|---|
 圧倒的スピード審査の事業者ローン【ファンドワン】
圧倒的スピード審査の事業者ローン【ファンドワン】5,000万円まで融資可能!
審査は最短40分
来店は原則不要で全国どこからでもご利用できます
最短即日でのお振込も実行可
「赤字決算」・「ビジネスローンは初めて」・「保証人を用意する事ができない」などでお悩みの事業主様もまずはお気軽にご相談ください。
<<ファンドワンが選ばれる理由>>
理由1:スピードと柔軟性を兼ね備えた審査
最短40分のスピード審査で、急を要する資金問題にも対応できます。
また。弊社独自の柔軟な審査基準を設けておりますので、赤字決算や税金・社会保険料の滞納を理由に、銀行等から融資を断られた事業主様への融資実績も豊富です。
理由2:大口の融資が可能
弊社はビジネスローンをはじめとする不動産担保ローン、売掛債権担保ローンなど多数の商品をご用意しており、大口のご融資にもご対応いたします。
理由3:安心の金利設定
弊社実質年率は2.5%~18.00%に設定しております。
ご相談時に詳しい金利のご説明をいたしますので、返済計画を立てた上でのお申し込みができます。
理由4:他社でご返済中でも幅広い選択肢で対応
銀行や信用金庫といった金融機関のほか、他のノンバンクで借り入れ中であっても条件次第でご利用可能です。
弊社の各種ローンでは複数あるお借入れを「おまとめ」して返済を一本化することが可能です。
おまとめすることで返済額や、管理の手間を軽減することができます。
| 総合評価 |
|---|
ファクタリングのメリット
1. 早期の資金調達
ファクタリングは、未来の売掛金を現金化する手段として機能します。これにより、事業者は売掛金の支払いを待つ必要なく、即座に資金を手に入れることができます。これは事業の成長や急な支出に対処するために非常に有益です。
2. 信用リスクの軽減
ファクタリング会社は、売掛金の回収を専門的に行うため、買掛先が支払いを遅らせたり、支払わなかったりするリスクを軽減します。これにより、事業者は信用リスクによる損失を回避できます。
3. 信用状況の向上
ファクタリングは、事業者の財務状況を改善する要因となります。売掛金を現金化することで、事業者は資産を増やし、負債を減らすことができ、信用スコアが向上する可能性があります。
4. 売掛金の管理効率向上
ファクタリング会社は売掛金の回収業務を代行し、事業者はそれにかかる時間と労力を節約できます。また、ファクタリング会社は売掛金の債権管理に専門知識を持っており、事業者は管理の効率向上を期待できます。
5. 資金繰りの安定化
ファクタリングにより、事業者は売上が発生するたびに資金を得ることができ、資金繰りの安定化が図れます。これにより、急な支出や経営上の困難に対処しやすくなります。
6. 創業企業に適している
特に新しい事業や創業企業にとって、ファクタリングは信用履歴や資産の不足により、伝統的な融資が難しい場合に有益です。ファクタリングは売掛金を利用するため、資産担保や信用スコアの要件が緩和されます。
7. 融資との併用が可能
ファクタリングは他の融資オプションと組み合わせて利用することができます。これにより、資金調達の多様な手段を活用し、事業の成長をサポートできます。
8. 顧客関係の維持
ファクタリングは売掛金を現金化するため、買掛先に対する支払いに影響を与えません。顧客関係を損なうことなく、資金調達を実現できます。
9. 柔軟性と適応力
ファクタリングは売掛金の一部を売却する形態であり、必要に応じて利用することができます。事業の成長や変化に適応するための柔軟な資金調達手段です。
10. 事業拡大の支援
ファクタリングにより、事業者は資金を獲得し、新しいプロジェクトや市場への進出をサポートできます。成長戦略の実現に貢献します。
11. 簡易な手続き
ファクタリングの手続きは比較的簡単で迅速です。伝統的な銀行融資よりも煩雑さが少なく、事業者にとって負担が軽減されます。
12. 事業者の専念
ファクタリングにより、事業者は売掛金の回収業務から解放され、本業に専念できます。時間とリソースを効果的に活用できます。
13. 利息の心配が不要
ファクタリングは貸付ではないため、利息の支払いが不要です。これは長期的なコスト面でのメリットと言えます。
14. 財務透明性の向上
ファクタリングは事業者に売掛金の実際の価値を明らかにします。これにより、正確な財務情報を提供し、投資家や取引先との信頼関係を築くのに役立ちます。
15. 現金フローの改善
ファクタリングは現金フローの改善に寄与します。定期的な売掛金の現金化により、事業の運営に必要な資金を確保しやすくなります。
16. 競争力の維持
ファクタリングを活用することで、競合他社に対して迅速な対応や大口取引への対応が可能となり、競争力を維持するのに役立ちます。
17. 経費削減
ファクタリングは売掛金の回収業務を外部に委託するため、従業員の給与や訓練にかかる経費を削減できます。
18. 売掛金の分散リスク
ファクタリングは売掛金を多くの買掛先に分散できるため、一つの取引先に依存しないリスク分散が可能です。
19. 信頼性の向上
ファクタリング会社のプロフェッショナリズムと経験を借りることで、取引先や投資家からの信頼性が向上します。
20. レバレッジの活用
ファクタリングを利用することで、売掛金を活用したレバレッジを実現できます。これにより、資本を最大限に活用し、事業の成長を促進できます。
ファクタリングは多くのメリットを提供し、事業の健全な成長や資金調達に役立つ手段と言えます。事業者は自身のニーズに合わせてファクタリングを活用し、ビジネスの成功に向けて利用できるでしょう。